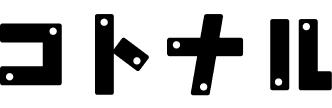「生きる意味や価値を考え始めると、われわれは気がおかしくなってしまう。生きる意味など、存在しないのだから」(ジークムント・フロイト)
書店に足をはこべば、「自分らしく働く」「やりがいのある仕事」「自己実現の方法」といったテーマの本がたくさん並んでいます。現代に生きる多くの人が、働くことの意味を探し求めていることのあらわれでしょう。
しかし、病気や事故で「働くこと」自体が難しくなることを想像したことがある人は少ないのでは?
今回取材したのは、書籍やラジオなどを通して文学作品を紹介する「文学紹介者」として活動し、『絶望名人カフカの人生論』など多くの著書を出版してきた頭木弘樹さん。2020年に出版した著書『食べることと出すこと』では、大学3年生のときに発病した潰瘍性大腸炎(※)によって食事も排せつも自分の意思で行うことが困難になり、人生が激変してしまった経験が素直な筆致でつづられています。

20歳から13年間という長い闘病生活を経て、「文学紹介者」という働き方にたどりついた頭木さん。「食べること」と「出すこと」と同じく「働くこと」に関しても、病気の経験を通して見えてきたことがあるようです。
ワークライフバランス、仕事のやりがい、収入やキャリアアップ、自分らしく働く、ダイバーシティや多様性──。現代社会を生きる私たちをとりまくさまざまなトピックスを交えながら、頭木さんにとって「働く」とはどのようなことなのかを聞きました。

頭木弘樹さん
文学紹介者。編訳書に『絶望名人カフカの人生論』(新潮文庫)など、著書に『絶望読書』(河出文庫)など、アンソロジーに『絶望図書館』『トラウマ文学館』(ちくま文庫)など。新刊に『落語を聴いてみたけど面白くなかった人へ』(ちくま文庫)、『食べることと出すこと』(医学書院 シリーズ ケアをひらく)
病気と向き合うなかでたどり着いた仕事

──「文学紹介者」とはどのようなお仕事なのでしょうか。
作品について「論じるのではなく、ただ紹介をする人」という立場を大切にしながら、さまざまな文学を紹介する仕事です。カフカやゲーテに関する本や落語の本の執筆、ラジオの出演など、仕事としてはいろいろやっているんですが、すべてに共通している基本が「ただ紹介をする」ということなんです。
──なぜ「ただ紹介をする」ということにこだわっているのですか?
「ただ紹介をする」ということは、あまり注目されませんが、とても重要なことだと僕は感じています。僕自身、実はもともと本をたくさん読むタイプでもなかったんですが、入院中に本を読むようになって、ドフトエフスキーの『カラマーゾフの兄弟』に夢中になったことがあったんですよ。
当時は6人部屋の病室だったんですが、僕が本を読んでいると同室の人たちが興味を持って、「どんな話?」と聞いてきてくれて。僕なりにカラマーゾフの兄弟を紹介してみると、「面白そうだな、俺も読む」と言って読んでくれました。すると、次第に病室の他の人たちにも「あの本が面白いらしいぞ」と広まって、病室内で『カラマーゾフの兄弟』が大流行したということがありました(笑)。
ビジネス書でさえイラストがないと読みたくないという人たちも、状況が合えば『カラマーゾフの兄弟』に夢中になれるんですね。そのきっかけをつくるのは、きっと「論評」ではない。遠くなってしまった文学と読者の距離を飛び石的にぽんぽんと渡っていくための、単純な「紹介」なのではないかと思うんです。
──なるほど。特に「文学」を紹介しようと思ったのも、そうした経験からなんでしょうか。
そうですねぇ。僕自身が入院中に文学に救われたというのは大きいかもしれません。特に古典文学には、非常に「暗い」ものがあると思うのですが、あの「暗さ」は、他の分野ではなかなか表現することが難しいんじゃないかと思います。
現代だと何事にもハッピーエンドを求められることが多いですし、古典文学のような、どーんと沈む「暗さ」のあるものを書くのは、今ではなかなか難しい。それでも、アウシュヴィッツの収容所でゲーテの文章に救われたという方がたくさんいるように、「『暗さ』に救われる」ということが人生にはあります。
僕も難病で入院していて、「もうこの先、健康な自分には戻れないんだ」と思い知らされる日々のなかで、明るい話なんてとても受け入れられませんでした。「願えば叶う」とか、「希望を捨てずに頑張ろう」とかいった励ましも余計につらくなってしまうくらいの絶望のなかでは、古典文学が持つ特有の「暗さ」が救いになったんです。古典文学の持つ力を信じているというのは、そういった原体験があるからかもしれません。
「働くこと」は、サバイバル
──頭木さんは、大学生の頃に潰瘍性大腸炎を発病したそうですが、その頃は「働くこと」に関してどのように考えていましたか?
当時はバブル経済で、学生たちは「就職先がありすぎて迷う」というような時代でした。フリーターも「自由なスタイルで格好いい」くらいに捉えられていた時期ですから、大学3年生なんて「これから先の人生、なんにでもなれるぞ」というタイミングだったんです。
僕も、まわりの学生と同じように人生を楽観視していて。何になりたいとか、何をしたいとか、そういう具体的なことを何も考えていない。そんな時期に、僕は潰瘍性大腸炎になり、選びきれないくらい存在していたはずの選択肢が急にゼロになってしまいました。
──突然選択肢を奪われるというのは、なかなかつらいものがありますよね......。
もう、お先真っ暗でしたねぇ。入院当初は、医者から「進学も就職も無理。親にずっと面倒をみてもらうしかない」ということも言われていました。
ですが、両親も歳をとるし、家が裕福なわけでもない。「自分で稼がなければ死んでしまう」という不安や恐怖がずっとありました。入院や治療や、病気になったことで必要になった衣類や器具など、とにかく何をするにもお金がかかりますからね。
当時はほとんど寝たきりでしたから、ベッドの上でできることで稼ぐしかないと思って、両親に無理を言ってワープロを買ってきてもらいました。寝たままの状態でも文字は打てるということを確かめて、「ライターならできるのでは?」と模索を始めたのが、僕にとって「働く」ことへの第一歩だったと思います。
──「好きなことを仕事に」という始まりではなく、生きるための手段だったんですね。

はい。「働くこと」は完全に自分が生きていくため、つまり「サバイバル」の手段でしたね。
まだ学生で何の知識も経験もありませんから、ライターといってもできることは本当に限られていました。「自分にできることって何だろう?」と考えて、受験の参考書のライティングなら手伝えるかもしれないと思い、応募したんですが「まだ学生でしょ? こういうのが書きたいなら予備校の先生にでもなってから応募してください」といったアドバイスをいただいて、「僕にはそれができないんだよ......!」というもどかしさを感じることもありましたね(笑)。
21歳くらいの頃からそうしたチャレンジを始めて、ひたすら応募しては落ち......を繰り返して、採用してもらえたのは数年後だったと思います。さらにそこから数年たって、年収が60万円になった時には感動して涙が出ましたよ。
手術後に直面した現実と、舞い込んだチャンス
──そんなライター時代から、今のような「文学紹介者」に至るきっかけは何だったんでしょうか。
発病から13年後に手術をすることになって、そのあとリハビリや自宅療養を長い期間続けていたのですが、手術した記念くらいの感覚で「これまでとはちょっと違う書きものをしたいな」と思うようになりました。
手術前に思い描いていた「もし治ったらこんなことがしたい」という妄想って、「エベレスト登頂」とか「深海」に潜るとか、そういう大冒険のようなことばかりだったんです(笑)。でも、実際に手術を終えた僕は、職歴も収入もあまりなく、35歳を過ぎていて、クレジットカードひとつもつくれないような大人になっていた。そういう現実に直面して、エベレストには登れないことを悟ったわけです。
それでも、「手術で症状が改善されたんだから、何かやらなくちゃ」という時に浮かんできたのが、「カフカについての本を書いてみたい」という思いでした。僕が入院中、カフカの言葉に何度も救われてきた経験があったからです。
それまで関わりのあった参考書の編集者さんから、文学系の編集さんにつなげてもらい、カフカに対する考察を伝えたりして、それをきっかけに念願のカフカの本を出版できました。
それを次の仕事につなげられたらよかったんですが、その出版社が倒産してしまって。本は書店から姿を消し、「幻の一冊」になってしまったんです。世の中のことを何も知らなかった当時の僕は、せっかく出版した一冊目の実績を使って営業をするようなこともできないまま、「誰かが見つけて、電話をくれるんじゃないか」という期待を胸に、電話を待つだけの日々になってしまいました。ただ、やがてその本が幸運な出会いを運んでくれるんですけれど。
──どんな出会いだったんでしょう?
ほそぼそとできることを続けながら暮らしていたなかで、編集者の品川さんという方が、僕の書いた幻の一冊を偶然図書館で見つけてくださって。「カフカについて、新しい本を書いてみませんか?」と電話をくれたんです。
もちろんとても嬉しいお声がけでしたが、その時は、カフカについて書くなら僕以外にももっと有名な方がたくさんいるだろうという思いもありました。なので、「僕じゃない人に頼んだ方がいいですよ」とお伝えしたんです。けれど、「どうしても頭木さんに」と言ってくださって、「あぁ、この人を失敗させちゃいけないな」という気持ちで、気合いを入れて執筆したのが『絶望名人カフカの人生論』です。

──その出版をきっかけに、頭木さんはNHK『ラジオ深夜便』に出演するなど、「文学紹介者」として活躍していくことになったと。ここでようやく「やりたいこと」に近づいてきた、という感じでしょうか。
うーん......「やりたいこと」という感じではないかもしれない。今でも、「働くこと」は基本的にサバイバルのためです。誰かの役に立ちたいとか、そういう思いもないわけではないですが、働く理由としてはそこがメインではなくて。やっぱり僕にとっての「働く」ということは、根底ではサバイバルのためのものなんじゃないかという気がします。
たとえば、僕は本が出るときに「みなさんぜひ買ってください」という表現を使います。親切な方は「お金のことを言っているように感じるので、『読んでください』という表現の方がいいのでは?」と言ってくださるんです。でも、僕としては「働く」ことは生きるためにやっていることなので、そこはやっぱり「読んでください」ではなく「買ってください」になるんですよね。
その次にくるモチベーションが、「憤り」です。僕の中では、「あるべきだけどまだない本を作りたい!」という思いが、とにかく強いんです。
──「あるべきだけどまだない本」、ですか。
たとえば今、病気などで絶望している方が手に取ることができる本って、ほとんどすべて「立ち直るため」の本なんです。だけど僕は、完治することのない難病を患って「立ち直ることができない」状態だったので、「なんでこういう時に読みたいと思える本がないんだ!」と、常に憤っていたんです。そんな憤りが、「絶望している方が手に取ることができる本」をつくりたい、という強い思いにつながっていますね。
あとは、声をかけてくださる編集者さんへの感謝と、出版した本やラジオについて何かを感じてくださった読者やリスナーさんからの感想が、今のモチベーションになっていると思います。
──仕事をサバイバルの方法として考えたら、自己啓発本など、「とにかく売れる本」を書くという方法もありそうです。あえて「絶望」をテーマにした本など、おそらく大衆ウケするわけではない本をつくるのはなぜでしょうか?
そうですね......、自分がサバイバルをしているからこそ、「人生のサバイバルをしている人に届く本がいい」と思っているからでしょうか。
本というものは、人間が本当に死にそうになった時に必要なものだと僕は思っています。往々にして、そうした絶望の淵に立たされている時に必要なのは、売れにくい本であり、派手な売れ方をする本ではないとも。
「『絶望名人カフカの人生論』と同じような本を、自己啓発系の内容に寄せて書けばもっと売れますよ」といったお話もたくさんいただきましたし、正直心は揺れました(笑)。でも、そこはぐっとこらえてお断りするようにしていました。
『絶望名人カフカの人生論』も、一度すべて書き終えてから「これはサバイバルが必要な人に届く内容になっているか?」「カフカが好きじゃない人にも知ってもらうための『紹介』になっているか?」と考えて、書き直したりもしました。
僕のミッションは、「人生のサバイバルをしている人に届く本」をつくり、基本的には売れないそういった本を、ちゃんと売れるようにするということなのかもしれません。
「人生の物語」を、書き直し続けて生きる
──近年、「自分らしく働く」ということがキーワードになっているように感じます。頭木さんは「自分らしさ」についてどのように考えられていますか?
僕自身は、20歳で、いわゆる「人生のレース」から外れてしまっています。就活もやっていませんし、会社勤めの経験もありません。ただ、入院中から仕事や就活に関する悩み相談を受けたり、学生から社会人になっていく知り合い達の姿を見ていたなかで、「人ってこんなにも変わってしまうんだ」という衝撃を受けた経験はあります。
無残に思えるくらい、みんな「◯◯らしい人」に変わっていくんですよね。会社員なら会社員らしい人、公務員なら公務員らしい人に。昔を知っている人からすれば「全然違う人になっちゃったな」と思うこともありますが、きっと本人はその人のままで生きているつもりでいる。そんな人たちに接していると、「自分らしいって何なんだろう?」と思ったりはします。
たとえば僕も、病気になる前と後では全然違って、やっぱり「病人らしい人」になりました。自分としては昔の自分のほうが本当の自分だと思っていますが、そんなことを言っていても仕方がなくて、今の自分でやっていくしかありません。
人生とは「自分がどの物語に出るか」によって書き直してくものだと思うんです。「どういう自分になりたいか」と考えても、病気や事故などによって「どの物語に出るか」が決められてしまうことがある。それに合わせて、書き直しをおこなっていくしかないんじゃないでしょうか。
──「書き直し」というと?
たとえば、僕の場合は大学生の時に、「青春物語」のなかの登場人物だったはずが、突然「難病物語」に変更になったわけです。そうなってくると、そのなかでどう立ち振る舞い生きていくのかは、変わって当然ですよね。
そんな風に、今の自分が置かれている状況に合わせて「物語を書き直す」ことが必要になる。そのためにはいろいろな物語を知っておく必要があると思うので、「人生の物語の書き直し」をするためにも、文学が役に立つと信じています。
──なるほど。頭木さんにとっての「書き直し」は、どのような内容だったんでしょうか。
僕の場合はどちらかといえば、「こういう物語に書き直そう」というより、「こういう物語には書き直さないでおこう」という部分に意識的になりました。一番避けようと思ったのは、「病気になってよかった」という物語に書き換えてしまうことです。

「さまざまな困難があったけれど、病気になってはじめてこういうことに気づけたのでよかった」といった物語は、周囲にも社会にも喜ばれますし、尊敬され歓迎されます。多分、社会復帰するためにも一番歩みやすくなるのではないでしょうか。
ただ、その物語の型に自分をはめてしまうのは、僕にとっては自己欺瞞。それに、そういう安住しやすい物語にはまってしまうと、その先もずっとその物語のなかでしか生きられなくなってしまうと感じています。
難病であるということは、「ずっと倒れている状態」ということ。そこから立ち上がって進んでしまえば、もうその人には見えなくなってしまうものがあるんです。大変ではあるけれど、その場で倒れ続けることで見えてくるものがあるんじゃないか。そんな考えから、僕は「倒れたまま、常に世の中に違和感を持ってジタバタしていないといけない」と思っています。なので「病気を受け入れろ」といくら言われても、それは拒否し続けるようにしているんです。
──「倒れたままでジタバタし続ける」のはつらくはないですか?
そうですね、抵抗し続けるという意味では大変なことでもあるかもしれません。もちろん、「病気になってよかった」という物語に描き直すことで救われる人もいると思いますし、それはそれで良いことだと僕も思います。
ただ、僕は文章を書く仕事を始めたからというのもあるのか、「物語」にはめてしまうことで失われてしまうものに意識を向けていたいな、と思うようになりました。
たとえば最近、映画や小説の感想で「主人公が成長していない」といった批評を目にすることがありますが、「主人公は必ず成長しないといけない」という考えが一般的にあるのかと驚かされました。本当は、成長しない物語もあっていいはずなのになぁ、と僕なんかは思うんですが(笑)。
とにかく、「人生の物語の書き直し」においては、そういうステレオタイプにはまってしまわないように、たくさんの物語を知っておいてほしいと思います。だからこそ、僕は「文学紹介者」として、たくさんの物語を知るきっかけを作っていきたいんです。
──たくさんの物語を知り、人生の物語を書き直し続けていくというのは、生き続けていく上でも非常に重要な視点ですね。
僕はコロナ禍の前は宮古島に住んでいたのですが、たとえば住む環境を変えるだけでも、物語の舞台設定が変わることでさまざまなルールが変化します。東京では「迷惑をかけない」文化だけれど、宮古島では「迷惑はかけあって当然」の文化なので、日常生活にしろ仕事にしろ、ルールがまったく違うんですよ。宮古島に飛行機でつくと、飛行機の荷物棚から知らない人が荷物をおろしてくれたり、障害があることを知らない人が車で送迎してくれたり。そんな光景を日々目にします。
お互い迷惑をかけあうことが当たり前になっているんですね。そういった環境が息苦しくて島を離れる方もいるんですけれど、「迷惑をかけない」文化よりも心地よく思う方もたくさんいると思うんです。
──今は新型コロナウイルス感染症の影響によって、物語の舞台設定が変わった方は多そうですね。
人間、生き続けていくためには「自分でコントロールできている感覚」を持つことが非常に重要なんだそうです。僕のような突然の発病もそうですが、今のような感染症のまん延も、人を強制的に引きこもり状態にしてしまいますよね。
そうした中でも、この舞台設定の中で自分でコントロールできる範囲を意識的に作ること、つまり物語を自らの手で書き直す感覚を持っておくということは重要なのかもしれませんね。
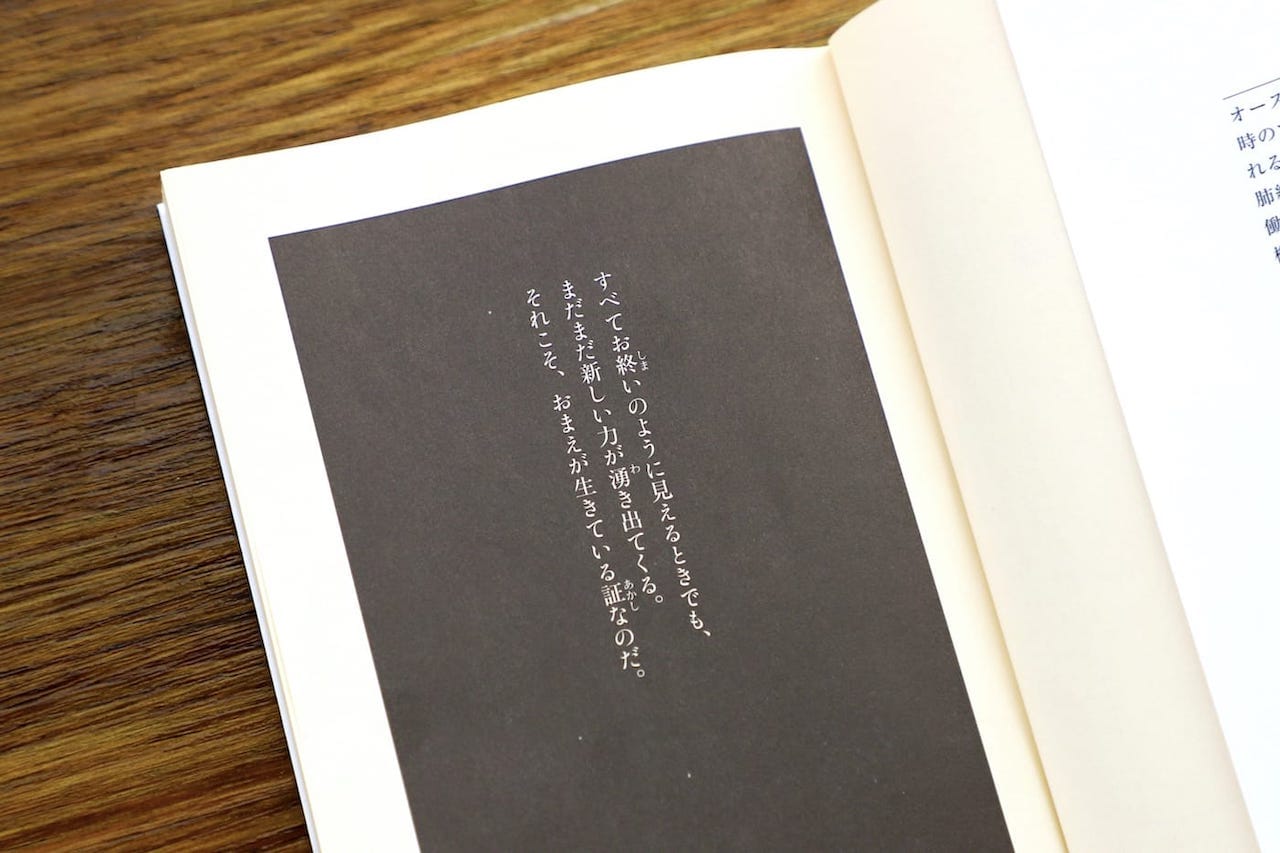
──最後に、難病や障害がある方や文化圏の異なる方と働く機会があり、どう接していいのか不安に思う方もいると思います。そうした方に何かアドバイスはありますか?
まずは前提として、「見えていないものがある」ということを認識することではないでしょうか。たとえば別の国の貧しい地域に行って「みんな元気で明るかった」と言う人がいる。でも実際は、元気で明るい人たち以外は亡くなっていたり、病院にいたりするだけかもしれません。「自分には見えていないものがあるのではないか?」という想像力を持っておくということは大切です。
ただ、「すべてを知る」というのは無理なことですし、最近は多様性を尊重することが求められる反動で、「多様性疲れ」によって差別や分断が助長されてしまっているようにも感じます。すべてを知るために頑張って、疲れてしまって、「それならもう会わないようにしよう」「近づかないようにしよう」という風になってしまうのでは、本末転倒ですよね。
全てを知らなかったとしても、目の前の人の話をちゃんと聞いて対応するということができていればいいと思うんです。「人には、いろいろな物語があるのだ」と意識しながら、傷つけることを過度に恐れず、知らない物語のことも面白がって知っていこうとする人が増えたらいいな、と僕は思っています。